Nova Advanced Cell Science Seminar 2022
培養細胞が
拓く未来
主催:ノバ・バイオメディカル
参加費
無料
無料
同時ライブ配信
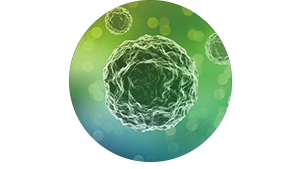
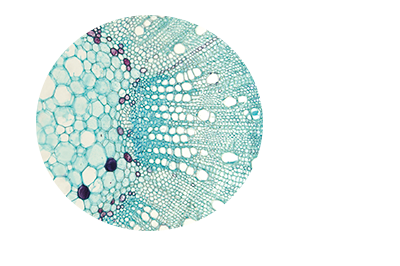
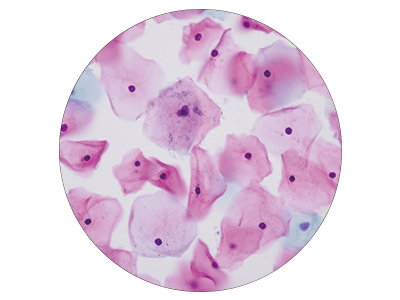
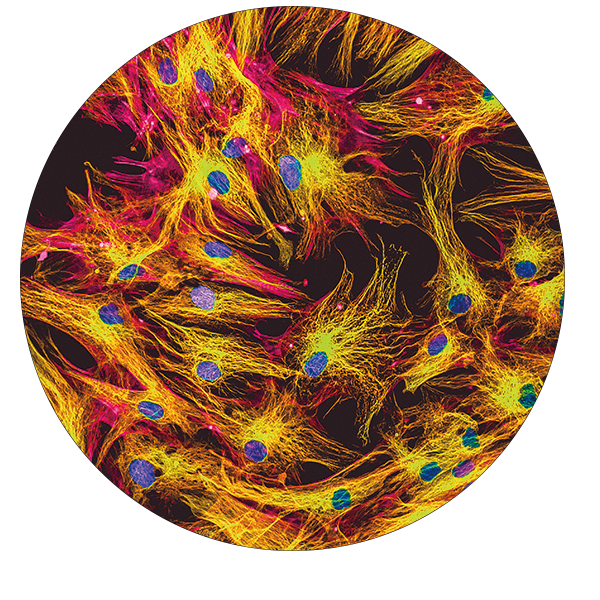
2022年9月6日(火) 10時~ 会場:AP品川 / 同時オンラインライブ配信 未来のバイオ医薬品製造 プログラム・抄録
※事前登録(無料)が必要です。
10:00 - 10:05 ご挨拶および本セミナーに関するご案内
動物細胞を用いたバイオ医薬品生産について考える -いまさら聞けない培地の重要性と今後の展開-
演者:大政 健史 先生 | 大阪大学大学院工学研究科 教授
≪講演概要≫
バイオ医薬品生産に用いられている株化細胞(細胞株:cell line)とは、もともと有限寿命である動物細胞が生体外に取り出されて培養しているうちに、生体であったころの機能の一部を失うものの無限増殖能をもち、あたかも微生物の培養のように、増殖させて増やすことができるようになったものを指す。現在のバイオ医薬品の生産には、チャイニーズハムスター卵巣由来細胞株(Chinese hamster ovary(CHO)細胞)に代表される細胞培養が主体となっている。現在細胞培養に用いられている培地は無血清の組成が明確なCD(Chemically defined)培地であり、さらに、培養中の様々な流加培地の添加方法や、培地成分や環境条件といった培養方法の工夫が、その生産性向上には欠かせない。本講演では、細胞培養とその代謝に焦点をあてて、これまでの細胞株培養の歴史的変遷や細胞培養方法の歴史、培地成分の解析の重要性、さらには培養方法等、講演者が行ってきた研究を中心に紹介したい。
1.大政健史(監修、著)「抗体医薬のための細胞構築・培養・ダウンストリームのすべて」シーエムシー出版(2015)
2.大政健史(監修、著)「抗体医薬のための細胞構築と培養技術」 シーエムシー出版 (2010)
3.大政健史 “生物化学工学分野における動物細胞工学に関する研究” 生物工学会誌 vol.99, No.1, pp.15-22 (2021). DOI: 10.34565/seibutukougaku.99.1_15
1.大政健史(監修、著)「抗体医薬のための細胞構築・培養・ダウンストリームのすべて」シーエムシー出版(2015)
2.大政健史(監修、著)「抗体医薬のための細胞構築と培養技術」 シーエムシー出版 (2010)
3.大政健史 “生物化学工学分野における動物細胞工学に関する研究” 生物工学会誌 vol.99, No.1, pp.15-22 (2021). DOI: 10.34565/seibutukougaku.99.1_15
AIを活用した最適培地組成の探索 ~少ない試行数で優れた培地を見出すポイント~
演者:小西 正朗 先生 | 北見工業大学工学部 教授
≪講演概要≫
生体触媒を用いた物質生産において、目的の物質や細胞の生産性や収率を得ることができる培地を見出すことは、経済性を担保する上で重要なポイントのひとつである。培地の最適化は古典的には1つの因子ごとの影響を実験的に検証するone-factor at a time (OFAT)により探索される。しかしながら、多様な成分を含む培地成分のすべてを検証するには、多くの時間と手間が必要になる。1970年代以降は統計学的な手法、例えば、田口メソッドを代表とする実験計画法(Design of Experiment (DoE))や表面応答法(RSM)による培地最適化に関する多くの研究が報告されている。DoEは、直交表による実験条件のデザインと分散分析もしくは重回帰分析を用いる。RSMは加えて多項式へのフィッティングと3次元グラフによる2変数の最適化の組合せを用いる。多くの研究で用いられているが、重要変数選択と重要変数による回帰モデル解析および検証といった構成がほとんどで、複数回の培養実験を必要とする。重回帰の発展形であるRasso回帰やRidge回帰は正則化項を加えることで、強く相関している独立変数による多重共線性問題に対応した解析法である。これらの手法は各独立変数の相関係数を比較することで、従属変数へのインパクトを容易に解釈できるため、解釈性が高い。重回帰分析の代わりに決定木(DTree)を用いた相関解析やそのアンサンブル解析であるランダムフォレスト(RFR)や勾配ブースティング(GBR)、ニューラルネットワーク(NN)等の教師つき機械学習モデルを採用することもできる。これらのアルゴリズムは予測精度が高いことが特徴であるが、DTree、RFR、GBRはクラス分類を目的としたアルゴリズムであるため、学習データよりも大きな従属変数(改善された培養結果)が得られない。NNはブラックボックス関数と呼ばれ解釈性が乏しい。しかしながら、近年、NNとブラックボックス関数を最適化できる遺伝的アルゴリズム(GA)を用いた培地や培養条件の最適化に関する研究が複数報告されている。演者はより効率的な培地最適化法を検討するため、深層学習(DNN)およびベイズ最適化(BO)を組合せて、大腸菌による緑色蛍光タンパク質(GFP)生産系をモデルとして、31種類の成分を含む合成培地の最適化について検討したところ、ラテン方格により設定した81条件実験データを基に、2回のDNN-BOにより、GFP生産効率を向上させることに成功している。また、分注ロボットやプレートリーダーを活用した培地最適化の効率化についても検討している。これらの具体的な事例を含めて、AI技術を活用した培地最適化の展望について紹介する。
ヒト幹細胞の大量培養工程設計に向けたアプローチ
演者:山本 陸 先生 | 大阪大学大学院 助教
≪講演概要≫
細胞の大量培養の規模は?という質問に対し,どれくらいのサイズを思い浮かべますか.酵母とビール工場が思い浮かぶ人は4 ~ 500000 Lくらいのタンクと答え,抗体生産によく用いられるチャイニーズハムスター卵巣細胞 (CHO細胞) が思い浮かぶ人は1000 L以上と答えるかもしれません.一方,ヒト人工多能性幹細胞 (hiPSC) やヒト間葉系幹細胞 (hMSC) などのヒト幹細胞の場合はどうでしょうか.「幹細胞」「大量培養」と検索を行い,出てくる論文で示される数値はhiPSCで0.1 ~ 1 L,hMSCでも1 ~ 50 L程度であり,文字通り桁が違います.これら幹細胞を用いた再生医療等の治療に必要な細胞数は,現在のところ患者1人あたり~109個と言われており,複数台の培養装置を駆使すれば今の培養規模でも一回の治療分は準備できます.しかし,将来的に幹細胞から複雑な組織や臓器を形成し,移植治療に用いる場合は,一回の治療に~1012個と,1000倍以上の細胞を準備する必要があります.またこれらの製品の非常に高い薬価を抑え,より身近な治療として普及させるためには, 一つのバッチでより多数の製品を生産し,他家 (同種) 移植などに利用する必要があり,今後より大規模な培養装置の開発が必須であると考えられます.
また,このようなヒト幹細胞を用いた治療では,培養された細胞そのものが製品となります.これは,工程設計において,細胞の代謝産物を利用する既存の工程とは異なるアプローチが必要であるとともに,細胞が工程中で”乱れる”ことに注視する必要があります.細胞の特性も大きく異なるため,培養によって新たな操作や工程の設計が必要となることもあります.
本発表では,これまでの培養装置・操作設計の考え方を振り返るとともに,ヒト幹細胞の特性に基づいた装置設計に関する考え方を紹介いたします.また,実際に最大10 L規模までのhiPSCの大量培養やhMSCの培養の経験,その中で行ってきた培地成分計測の結果などに基づき,今後,より大規模な培養装置や工程設計に必要とされるであろう考え方について紹介いたします.
ザルトリウスが提供する培地最適化サービスと培地ポートフォリオ
演者: 秋山 栞里 様
ザルトリウス・ステディム・ジャパン株式会社
フィールドアプリケーションスペシャリスト(細胞株開発、培地、各種試験)
バイオリアクター稼働状況をデジタルツインで監視 - QbD構築へ…
演者: 柏屋 滋 様 シーメンスプロセスシステムズエンジニアリング
BioProfile FLEX2を用いた細胞の“健康診断”
演者: 大渕 徹
ノバ・バイオメディカル株式会社 営業部
演者: 寒川 剛 様
株式会社テクノプロ テクノプロ・R&D社
事業統括部 神戸リサーチセンターグループリーダー
セミナー参加申込はこちらから
セミナーに関するご案内は、セミナー事務局(novabio-seminar@jtbcom.co.jp)およびノバ・バイオメディカル(jp-marketing@novabio.com)よりご連絡いたします。
ドメイン指定をされている場合は@jtbcom.co.jpおよび@novabio.comのドメインを受信できるように設定してください。
ノバ・バイオメディカル株式会社 セミナー事務局 jp-marketing@novabio.com
セミナー受付窓口:JTBコミュニケーションデザイン novabio-seminar@jtbcom.co.jp